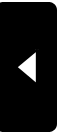2011年07月01日17:34
見たい祭≫
カテゴリー │見聞
善さんのように、大したことは書けませんが、たまたま写真を整理していたらいい画がありましたので。
舞阪の岐佐神社祭典
毎年旧暦の9月14日,15日に行われるお祭で、お祭の進行すべてが分刻み。
大変規律正しい、見ているこっちも背筋が伸びるようなお祭です。
何が見たくて足を運ぶって、やっぱりここのお祭には自分たちの持っていないものがたくさんあるから行ってしまうのです。

「舞阪の青年衆のための祭」という意識が高く。非常にうらやましいんです。
毎年指をくわえながら見ています。

舞阪の町を歩けば、どこの家も玄関と道沿いにある部屋の窓が開いていてその中では法被を着た人たちが楽しそうに飲んでいて
子供たちは青年衆の太鼓より少し小さな太鼓を叩いているが、青年衆顔負け
女性衆は手踊り
漁港に行けば、ほとんどの漁船に大漁旗があがっている。

町全体でお祭をやっている感じが好きです。

何番使い(であってましたっけ?)の帰りは法被を裏返して帰るようですが
法被の裏地もいちいちお洒落。
そこの祭の歴史はあまりわかりませんが、カメラを持ってお祭見物に行くと
ふといい画があったりします。
凧も、何も言わんでも見ている方が「すごい!!」ってなるような祭にしていきたいですね。
(ip)
舞阪の岐佐神社祭典
毎年旧暦の9月14日,15日に行われるお祭で、お祭の進行すべてが分刻み。
大変規律正しい、見ているこっちも背筋が伸びるようなお祭です。
何が見たくて足を運ぶって、やっぱりここのお祭には自分たちの持っていないものがたくさんあるから行ってしまうのです。

「舞阪の青年衆のための祭」という意識が高く。非常にうらやましいんです。
毎年指をくわえながら見ています。

舞阪の町を歩けば、どこの家も玄関と道沿いにある部屋の窓が開いていてその中では法被を着た人たちが楽しそうに飲んでいて
子供たちは青年衆の太鼓より少し小さな太鼓を叩いているが、青年衆顔負け
女性衆は手踊り
漁港に行けば、ほとんどの漁船に大漁旗があがっている。

町全体でお祭をやっている感じが好きです。

何番使い(であってましたっけ?)の帰りは法被を裏返して帰るようですが
法被の裏地もいちいちお洒落。
そこの祭の歴史はあまりわかりませんが、カメラを持ってお祭見物に行くと
ふといい画があったりします。
凧も、何も言わんでも見ている方が「すごい!!」ってなるような祭にしていきたいですね。
(ip)
この記事へのコメント
素敵な写真ばかりですね~。
僕も漁師町舞阪の祭りが大好きで毎年行っています。
去年思ったのが、伝統に厳しいことは勿論だけどガチガチな雰囲気だけじゃないということ。
町全体からの青年への絶大な信頼感が見ていて感じられます。
年代によって祭りの役割が違ったり、そのときその場面で締めるところと騒ぐとこのメリハリが「自然」で気持ちいいですね。
僕も漁師町舞阪の祭りが大好きで毎年行っています。
去年思ったのが、伝統に厳しいことは勿論だけどガチガチな雰囲気だけじゃないということ。
町全体からの青年への絶大な信頼感が見ていて感じられます。
年代によって祭りの役割が違ったり、そのときその場面で締めるところと騒ぐとこのメリハリが「自然」で気持ちいいですね。
Posted by naka at 2011年07月02日 00:08
よく、祭の改変を迫る観光との対比で、「見せるもんじゃない、やるもんだ」とかなんとか聞きます。が、ほんとにいい祭りはやはり見ていても楽しいし、見せるだけのことがあると思いますわ。
祭にとって大事な要素のひとつに「図案」がありますが、図案はすなわちビジュアルですから、当然美しく見せるという意図がそこにはあるわけですね。
祭にとって大事な要素のひとつに「図案」がありますが、図案はすなわちビジュアルですから、当然美しく見せるという意図がそこにはあるわけですね。
Posted by 善 at 2011年07月02日 00:35
良い写真だね!
法被を裏返して着てるのは見たことなかったな~今の若者って「そうやって」着るってことも知らんだろうね。
老若男女がメリハリもって楽しんでる祭り。
見ていて楽しい大好きな祭りだな。舞阪。
法被を裏返して着てるのは見たことなかったな~今の若者って「そうやって」着るってことも知らんだろうね。
老若男女がメリハリもって楽しんでる祭り。
見ていて楽しい大好きな祭りだな。舞阪。
Posted by Y at 2011年07月02日 01:57
善さん
そうなんですよ。
よその町より威勢のいい練りとか凧の技術とか屋台、お囃子だって当然見られることを意識した表れですもんね。自町の揃いの法被を着ているということはそういうことだと。
そうなんですよ。
よその町より威勢のいい練りとか凧の技術とか屋台、お囃子だって当然見られることを意識した表れですもんね。自町の揃いの法被を着ているということはそういうことだと。
Posted by naka at 2011年07月02日 10:21
失礼してコメントさせていただきます。
舞阪っていうと、「お神輿を見下ろしちゃいけない」とかいろいろな決まりがあるけど、そのしきたりも含めて祭の楽しさ、面白さになってる。
それと、「兄弟分」のシステムが、今でもいい意味で町の生活や祭の伝統を維持しているのが見て分かる。
その向うに見えるのが、残したいもの、残さなきゃいけないものなんでしょうね。
舞阪っていうと、「お神輿を見下ろしちゃいけない」とかいろいろな決まりがあるけど、そのしきたりも含めて祭の楽しさ、面白さになってる。
それと、「兄弟分」のシステムが、今でもいい意味で町の生活や祭の伝統を維持しているのが見て分かる。
その向うに見えるのが、残したいもの、残さなきゃいけないものなんでしょうね。
Posted by 酒上不埒 at 2011年07月03日 20:24