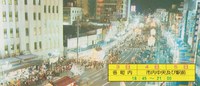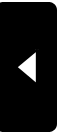2014年03月21日03:19
終了時刻ばかりではあるまい≫
カテゴリー │終了時刻
まつりの終了時刻を「公式に23時まで延長」としたいとする「組織委員会」(=旧「本部」)が、関係機関(主には所轄警察署)に対して、道路使用許可時間の延長を求めた、そして、それは現段階では「検討継続」となった、と経緯を説明する新聞記事。

『中日新聞』2014年3月16日(日)付34面より
この記事には、言葉の用い方を含め、いろいろなところに違和感を覚えるのですが、この際、用語の点は後回し。
公式に「22時をもって終了」は昔から。
一方で、現実的には22時には終っていない、22時過ぎに終われば「今日はずいぶん早く終ったな」となり、「何かあったのか」とかえって心配されそうなもの。
これもまた昔っから。
(記事でいうところの「一部の町内で終了できない」「見過ごされてきた」は、事実をとらえていないように思います。)
(こちらには戦前の回顧録の一部)
http://takoken.hamazo.tv/e5191236.html(14年3月11日)
この祭は昔から、
19時頃から引きはじめた屋台を21時過ぎに格納して、そこから初練りへと向かうわけであります。
初練りは初凧を揚げ合戦をし屋台を引いてきた青年連を慰労するための祝宴、という性質があるので、21時過ぎに出発して、2軒回っても23時をまわることになってしまうのです。
で、「制度上の終了」と「実際の終了」には時間的な開きがあるまま、ずーっと今まで来ていたのですが、ここへ来て、「苦情」なるものが増えた。(とされる)。
終了時刻にのみついて言うと、戦前にさかのぼってもほぼ事情は同じなのに、ここ数年で「苦情」が増えた。(とされる)。
「祭に対する地域の理解」が、ややゆらぎつつある、ということになります。
(批判を恐れずにいえば、コトを知らない人が増えた」とも)
「凧が22時に終わらないとは何事だ、迷惑だ」と警察に苦情を言うのは、極論すれば、「コーヒーが熱いとは知らなかった、ヤケドした」と訴えた訴訟と同じ滑稽さがあります。少なくとも昔からやっている区域では。
「ありゃ外から来た衆だからコトを知らん」
冷やかにいうと、こうなってしまいますが、もう一歩踏み込んで考えてみましょう。
終了時刻がそんなに変わっていないのに、なぜ、「苦情」が増えた(とされる)のか?
一つには、「住民人口の流動化」(というとおカタイ感じですが)。
要するに、再開発などで昔っからの住民が区域外へ流出して、分譲マンションや賃貸住宅などの新住民が流入している、という事。
浜松は都心であればあるほど、凧まつりの盛んな地域になっているので、古くからの町内ほどこの問題に頭を悩ませていることでしょう。
でも。
仮にそうであっても(=マンション建設で新住民が増えたとしても)、「遅い時間まで音が鳴っている」「遅い時間に人々が楽しんでいる」、ことにたいして理解があれば、「苦情」にはならないはず。
理想論ですが。
苦情になってしまうのは、そこに「住民同士の関係の希薄さ」があったりするもの。
「マンションに住んでると、隣の人の顔も知らない」などとは、日本全国どこでも言われることでありまして、「顔も知らないだれか」から、あんな大きな音のラッパや太鼓や掛け声が飛んでくれば、そりゃ文句も言いたくもなるでしょう。
でも、近所を知らないから文句をいう相手も分からない。
そこで「110番」となってしまう。
でも、どういう人が一所懸命に祭の維持に努めて奔走しているのか、その人々の人柄や苦労を少しでも知れば、「若い衆、一所懸命やってるでなァ」という理解も生まれてくるでしょう。
ひとつには、こうった「地域社会の人口の流動化」という問題があるのだと思います。
これは、祭が悪いわけでもなければ、マンションが悪いわけでもない。
ただ、ここ数年で、マンションの建設が相次いで、地域人口が急激に流動化しつつあることも確か。
したがって、否応なしに、各町内の住民の関係を形成していかなければいかんのです。少なくとも、警察を介さなくても、お互いに言いたいことをさらっと言い合える関係が作られるのが理想。
新住民もふくめた、新しい関係づくりが急務となってまいります。
(善)

『中日新聞』2014年3月16日(日)付34面より
この記事には、言葉の用い方を含め、いろいろなところに違和感を覚えるのですが、この際、用語の点は後回し。
公式に「22時をもって終了」は昔から。
一方で、現実的には22時には終っていない、22時過ぎに終われば「今日はずいぶん早く終ったな」となり、「何かあったのか」とかえって心配されそうなもの。
これもまた昔っから。
(記事でいうところの「一部の町内で終了できない」「見過ごされてきた」は、事実をとらえていないように思います。)
(こちらには戦前の回顧録の一部)
http://takoken.hamazo.tv/e5191236.html(14年3月11日)
この祭は昔から、
19時頃から引きはじめた屋台を21時過ぎに格納して、そこから初練りへと向かうわけであります。
初練りは初凧を揚げ合戦をし屋台を引いてきた青年連を慰労するための祝宴、という性質があるので、21時過ぎに出発して、2軒回っても23時をまわることになってしまうのです。
で、「制度上の終了」と「実際の終了」には時間的な開きがあるまま、ずーっと今まで来ていたのですが、ここへ来て、「苦情」なるものが増えた。(とされる)。
終了時刻にのみついて言うと、戦前にさかのぼってもほぼ事情は同じなのに、ここ数年で「苦情」が増えた。(とされる)。
「祭に対する地域の理解」が、ややゆらぎつつある、ということになります。
(批判を恐れずにいえば、コトを知らない人が増えた」とも)
「凧が22時に終わらないとは何事だ、迷惑だ」と警察に苦情を言うのは、極論すれば、「コーヒーが熱いとは知らなかった、ヤケドした」と訴えた訴訟と同じ滑稽さがあります。少なくとも昔からやっている区域では。
「ありゃ外から来た衆だからコトを知らん」
冷やかにいうと、こうなってしまいますが、もう一歩踏み込んで考えてみましょう。
終了時刻がそんなに変わっていないのに、なぜ、「苦情」が増えた(とされる)のか?
一つには、「住民人口の流動化」(というとおカタイ感じですが)。
要するに、再開発などで昔っからの住民が区域外へ流出して、分譲マンションや賃貸住宅などの新住民が流入している、という事。
浜松は都心であればあるほど、凧まつりの盛んな地域になっているので、古くからの町内ほどこの問題に頭を悩ませていることでしょう。
でも。
仮にそうであっても(=マンション建設で新住民が増えたとしても)、「遅い時間まで音が鳴っている」「遅い時間に人々が楽しんでいる」、ことにたいして理解があれば、「苦情」にはならないはず。
理想論ですが。
苦情になってしまうのは、そこに「住民同士の関係の希薄さ」があったりするもの。
「マンションに住んでると、隣の人の顔も知らない」などとは、日本全国どこでも言われることでありまして、「顔も知らないだれか」から、あんな大きな音のラッパや太鼓や掛け声が飛んでくれば、そりゃ文句も言いたくもなるでしょう。
でも、近所を知らないから文句をいう相手も分からない。
そこで「110番」となってしまう。
でも、どういう人が一所懸命に祭の維持に努めて奔走しているのか、その人々の人柄や苦労を少しでも知れば、「若い衆、一所懸命やってるでなァ」という理解も生まれてくるでしょう。
ひとつには、こうった「地域社会の人口の流動化」という問題があるのだと思います。
これは、祭が悪いわけでもなければ、マンションが悪いわけでもない。
ただ、ここ数年で、マンションの建設が相次いで、地域人口が急激に流動化しつつあることも確か。
したがって、否応なしに、各町内の住民の関係を形成していかなければいかんのです。少なくとも、警察を介さなくても、お互いに言いたいことをさらっと言い合える関係が作られるのが理想。
新住民もふくめた、新しい関係づくりが急務となってまいります。
(善)