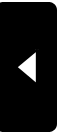2013年09月04日00:29
法被の図案について≫
カテゴリー │図案
ご無沙汰しております。
今年は某団体青年部のアタマを仰せつかっていたり、某事業の事務局だったりして、クビが回っておりません。スミマセン。
8月20日(19日深夜)にコメントをいただいておりました。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
二俣祭•浜松凧揚祭•掛川祭•三熊野神社大祭など様々な地域に法被があります。共通点が各地域ありますね
ただ最近の浜松凧揚祭に衿文字の書体や背紋に関して江戸文字を使用しており、なおかつ藍染(限りなく黒に近い青•紺 )の法被が増えているように感じ、見分けがつけません。
それがだめだと否定も、肯定もいたしません。
素朴なんですが何故なんでしょうか。
大雑把で申し訳ありませんが、原因となる?理由などあれば参考にしたいです
Posted by 雄山神社 at 2013年08月20日 00:39
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
何故か?とご質問であります。
「なぜ見分けがつかないのか?」ではなく、「なぜ ~な法被が増えているのか」について訊かれていると理解します。
「江戸文字」というのは、書体の類のこと。
歌舞伎で用いる「勘亭流」や、寄席で用いる「寄席文字」や、相撲で用いる「相撲文字」とか、千社札や江戸の法被で用いられていた「籠字」のことを総称して言うのだそうです。
コチラでご覧いただけます。(お手軽ですみませんが、Wikipediaより)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%96%87%E5%AD%97
その中で、「最近増えたと感じられている」というのは、ここ20年の間に急速に増えた、個人が誂える法被に多いもの。
籠文字から創り出された「千社文字」という規格書体を多用している法被のことでしょう。
ここからは、この20年間の私の見聞に基づく妄想です。
【妄想】
この25年くらい前=1980年代末期から「祭用品専門店」なる業種が登場しました。
浜松では、常盤町の春雨通りにあった「凧人(かいと」)、駅南の「てら田」、千歳町の「加茂江(かもえ)屋」、板屋町の「祭すみたや」あたりが早かったと思います(敬称略)。
それまで、祭で用いる装束は季節になると履物店とか洋品店とかに並んだそうです。今でもお盆の前になるとお飾りに使う麻の茎が並んだりするのと同じですね。
それが、この頃から「祭用品」をキーワードに、関連する商品を集めた上記の店舗が登場します。
流通には、小売店の前には問屋があるわけで、その前にはメーカーが存在します。
この「祭用品専門店」なるものは、おそらく東京あたりの祭用品メーカーが仕掛けた新しい商売なのだと思います。
前述の加茂江屋さんは元は履物店(「千歳町の履物屋さん」というだけで「街の商売だなァ」というオシャレな感じがします)、祭すみたやさんは「板屋町すみたや」といって3月5月の人形や花輪などを扱う「際物店」でした。
法被の需要は、本来、町内の法被ですから、注文者は町内の機関(青年会や祭組織=浜松では凧揚会)になり、今でもそれはそれで残っていますが、祭用品専門店が、個人消費向けに法被を売り始めました。
その時に、祭用品専門店も、今までとおなじ物を扱っていたのでは商売になりません。町内が染物店などに発注していた従来の法被を、敢えて扱う意味はないのです。
そこで「江戸で染める藍染半天」などというキャッチコピーを打ち、「今までと違うもの」を「今までと違うルート」で売り始めました。
【従来の法被流通ルート】
染物店 →町内組織 →町内の担い手
【祭用品ビジネスによる新ルート】
祭用品メーカー →問屋 →小売店 →個人
「祭の本場=江戸」というイメージ、「本物=藍染」というイメージ。
こういうイメージと共に新規需要と新規市場を創り出したのであります。
その時に、「江戸文字」、とくに「千社文字」も、誰でも扱える規格書体として、「祭の本場=江戸」のイメージを支えながら付随してきました。
こんなところじゃないかなァと妄想しております。
雄山神社様。
答えになりましたでしょうか。
妄想ですが。
(善)
画像はイメージです。妄想の内容とは無関係です。

(2010年1月撮影)
別誂えの法被、といいつつ、「規格化された書体」を用いられてしまうあたり、浜松の人も「人がいい」というか、なんというか。
今年は某団体青年部のアタマを仰せつかっていたり、某事業の事務局だったりして、クビが回っておりません。スミマセン。
8月20日(19日深夜)にコメントをいただいておりました。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
二俣祭•浜松凧揚祭•掛川祭•三熊野神社大祭など様々な地域に法被があります。共通点が各地域ありますね
ただ最近の浜松凧揚祭に衿文字の書体や背紋に関して江戸文字を使用しており、なおかつ藍染(限りなく黒に近い青•紺 )の法被が増えているように感じ、見分けがつけません。
それがだめだと否定も、肯定もいたしません。
素朴なんですが何故なんでしょうか。
大雑把で申し訳ありませんが、原因となる?理由などあれば参考にしたいです
Posted by 雄山神社 at 2013年08月20日 00:39
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
何故か?とご質問であります。
「なぜ見分けがつかないのか?」ではなく、「なぜ ~な法被が増えているのか」について訊かれていると理解します。
「江戸文字」というのは、書体の類のこと。
歌舞伎で用いる「勘亭流」や、寄席で用いる「寄席文字」や、相撲で用いる「相撲文字」とか、千社札や江戸の法被で用いられていた「籠字」のことを総称して言うのだそうです。
コチラでご覧いただけます。(お手軽ですみませんが、Wikipediaより)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%96%87%E5%AD%97
その中で、「最近増えたと感じられている」というのは、ここ20年の間に急速に増えた、個人が誂える法被に多いもの。
籠文字から創り出された「千社文字」という規格書体を多用している法被のことでしょう。
ここからは、この20年間の私の見聞に基づく妄想です。
【妄想】
この25年くらい前=1980年代末期から「祭用品専門店」なる業種が登場しました。
浜松では、常盤町の春雨通りにあった「凧人(かいと」)、駅南の「てら田」、千歳町の「加茂江(かもえ)屋」、板屋町の「祭すみたや」あたりが早かったと思います(敬称略)。
それまで、祭で用いる装束は季節になると履物店とか洋品店とかに並んだそうです。今でもお盆の前になるとお飾りに使う麻の茎が並んだりするのと同じですね。
それが、この頃から「祭用品」をキーワードに、関連する商品を集めた上記の店舗が登場します。
流通には、小売店の前には問屋があるわけで、その前にはメーカーが存在します。
この「祭用品専門店」なるものは、おそらく東京あたりの祭用品メーカーが仕掛けた新しい商売なのだと思います。
前述の加茂江屋さんは元は履物店(「千歳町の履物屋さん」というだけで「街の商売だなァ」というオシャレな感じがします)、祭すみたやさんは「板屋町すみたや」といって3月5月の人形や花輪などを扱う「際物店」でした。
法被の需要は、本来、町内の法被ですから、注文者は町内の機関(青年会や祭組織=浜松では凧揚会)になり、今でもそれはそれで残っていますが、祭用品専門店が、個人消費向けに法被を売り始めました。
その時に、祭用品専門店も、今までとおなじ物を扱っていたのでは商売になりません。町内が染物店などに発注していた従来の法被を、敢えて扱う意味はないのです。
そこで「江戸で染める藍染半天」などというキャッチコピーを打ち、「今までと違うもの」を「今までと違うルート」で売り始めました。
【従来の法被流通ルート】
染物店 →町内組織 →町内の担い手
【祭用品ビジネスによる新ルート】
祭用品メーカー →問屋 →小売店 →個人
「祭の本場=江戸」というイメージ、「本物=藍染」というイメージ。
こういうイメージと共に新規需要と新規市場を創り出したのであります。
その時に、「江戸文字」、とくに「千社文字」も、誰でも扱える規格書体として、「祭の本場=江戸」のイメージを支えながら付随してきました。
こんなところじゃないかなァと妄想しております。
雄山神社様。
答えになりましたでしょうか。
妄想ですが。
(善)
画像はイメージです。妄想の内容とは無関係です。

(2010年1月撮影)
別誂えの法被、といいつつ、「規格化された書体」を用いられてしまうあたり、浜松の人も「人がいい」というか、なんというか。