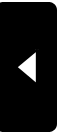2021年04月21日22:51
心配しておりました≫
カテゴリー │「浜松まつり」諸問題
本日の『中日新聞』記事(電子版より)。
「浜松の凧作り業者苦境 注文激減、売り上げ1割」
2021年4月21日 05時00分 (4月21日 05時03分更新)
https://www.chunichi.co.jp/article/240262

抜粋
〈 新型コロナウイルスの感染拡大で、規模が縮小される浜松まつり(五月三〜五日)の呼び物の凧を作る業者が、苦境に立たされている。昨年の中止に続き、今年は凧の注文が激減。各町が注文する凧の大半は浜松市内の二業者で手掛けているだけに、コロナ禍で経営の厳しさが続けば、「継承してきたまつりの伝統にも影響が出かねない」と懸念する声が市民からも上がっている。(後略) 〉
売上9割減!!。
衝撃的な数字です。
そりゃ「出口」を止められたようなもの。
新コロナに感染して死ぬリスクより、経済的に殺されるリスクの方がリアルに目の前に迫っている、ということです。
2021年1月1日記事(「新年を迎えまして 21/01/01」)にも書きましたが。
https://takoken.hamazo.tv/e9019682.html
〈上西すみたや〉さんも〈一瀬堂〉さんも、浜松において100年以上の業歴をお持ち。
押しも押されぬ老舗です。
凧は、素材としては「竹、和紙、麻、銅線、ロウ、染料」でできております。
そして。
「竹を割る」「竹の曲がりを直す」「紙を継ぐ」という技術の上に。
凧屋さんの「竹を組む」「紙を張る」「下絵を描く」「ロウを入れる」「色を付ける」という独自技術が加えられて完成します。
「竹を割る」のは傘屋さんの技術。
「竹の曲がりを直す」のは籠屋さんの技術。
「紙を継ぐ」のは表具屋さんの技術。
傘屋さんと言ったって、もちろん洋傘ではありませんからね。
和傘も竹の籠も表具も、高度成長期以前からの職人さんの技術。
これらは、住宅や生活用品の機械生産化で、廃れた生業になってしまいました。
凧も、もちろん高度成長期以前の生業の一つ。
ですが、社会の基盤が大きな変化を遂げる中、年に1回のまつりの主要アイテムとして存在し続けたところに、残っていく要素があった。
前の時代から、今も変わらず継続してる生業やその技術を「伝統」と呼ぶのであれば。
「凧揚祭」も「浜松凧」も、紛れもなく「伝統」的なるもの。
なぜなら、浜松凧や凧合戦が盛んだった約110年~140年前頃には、発生し発展したが、現代においては同じアイテムは自然のなりゆきでは絶対に発生しないから。
反対に、その気で守らなければ、滅びることも大いに有り得えます。
浜松において特筆すべきは。
凧合戦発生当時に創業している2つの店「すみたや」と「一瀬堂」が、今の今まで、「文化財保護」のような対象ではなく、「商売」として継続している点。
「旧町内」だけでも66町あった祭の規模があって、これが支えられてきた。
同時に、毎年各組が激しく消耗する凧揚祭は、この2業者があってこそ成り立ってきた。
浜松凧を扱う店は、浜松以外には絶対に存在しないという事実。
そう考えれば浜松にとって文字通り「かけがえのない」存在なのであります。
この中日新聞の記事は、今季、もっとも素直に読める(ただし深刻な事情を伝えている)記事でした。
(善)
「浜松の凧作り業者苦境 注文激減、売り上げ1割」
2021年4月21日 05時00分 (4月21日 05時03分更新)
https://www.chunichi.co.jp/article/240262

抜粋
〈 新型コロナウイルスの感染拡大で、規模が縮小される浜松まつり(五月三〜五日)の呼び物の凧を作る業者が、苦境に立たされている。昨年の中止に続き、今年は凧の注文が激減。各町が注文する凧の大半は浜松市内の二業者で手掛けているだけに、コロナ禍で経営の厳しさが続けば、「継承してきたまつりの伝統にも影響が出かねない」と懸念する声が市民からも上がっている。(後略) 〉
売上9割減!!。
衝撃的な数字です。
そりゃ「出口」を止められたようなもの。
新コロナに感染して死ぬリスクより、経済的に殺されるリスクの方がリアルに目の前に迫っている、ということです。
2021年1月1日記事(「新年を迎えまして 21/01/01」)にも書きましたが。
https://takoken.hamazo.tv/e9019682.html
〈上西すみたや〉さんも〈一瀬堂〉さんも、浜松において100年以上の業歴をお持ち。
押しも押されぬ老舗です。
凧は、素材としては「竹、和紙、麻、銅線、ロウ、染料」でできております。
そして。
「竹を割る」「竹の曲がりを直す」「紙を継ぐ」という技術の上に。
凧屋さんの「竹を組む」「紙を張る」「下絵を描く」「ロウを入れる」「色を付ける」という独自技術が加えられて完成します。
「竹を割る」のは傘屋さんの技術。
「竹の曲がりを直す」のは籠屋さんの技術。
「紙を継ぐ」のは表具屋さんの技術。
傘屋さんと言ったって、もちろん洋傘ではありませんからね。
和傘も竹の籠も表具も、高度成長期以前からの職人さんの技術。
これらは、住宅や生活用品の機械生産化で、廃れた生業になってしまいました。
凧も、もちろん高度成長期以前の生業の一つ。
ですが、社会の基盤が大きな変化を遂げる中、年に1回のまつりの主要アイテムとして存在し続けたところに、残っていく要素があった。
前の時代から、今も変わらず継続してる生業やその技術を「伝統」と呼ぶのであれば。
「凧揚祭」も「浜松凧」も、紛れもなく「伝統」的なるもの。
なぜなら、浜松凧や凧合戦が盛んだった約110年~140年前頃には、発生し発展したが、現代においては同じアイテムは自然のなりゆきでは絶対に発生しないから。
反対に、その気で守らなければ、滅びることも大いに有り得えます。
浜松において特筆すべきは。
凧合戦発生当時に創業している2つの店「すみたや」と「一瀬堂」が、今の今まで、「文化財保護」のような対象ではなく、「商売」として継続している点。
「旧町内」だけでも66町あった祭の規模があって、これが支えられてきた。
同時に、毎年各組が激しく消耗する凧揚祭は、この2業者があってこそ成り立ってきた。
浜松凧を扱う店は、浜松以外には絶対に存在しないという事実。
そう考えれば浜松にとって文字通り「かけがえのない」存在なのであります。
この中日新聞の記事は、今季、もっとも素直に読める(ただし深刻な事情を伝えている)記事でした。
(善)