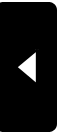2016年03月01日00:03
報告(第5回)③≫
カテゴリー │凧合戦
先般、「報告会」の第5回目をひっそりと開催いたしました。
今回のテーマは昨年に引き続き「凧合戦」。
今回は、「歴史」に焦点をあてて展開を致しました。
サブタイトルも「~凧揚祭前史~」。
昔は5日間だった。 →今は3日間。
昔は練兵場だった →今は中田島。
戦後の経緯の中で、「昔は~だった」という形が、現在のものへと変化していくわけです。
その「昔の姿」は、どうやって出来上がったのか。
今回は、やや踏み込んだ内容を展開。
初凧は江戸時代からあった。
初凧は農村でもあった。
今の鯉のぼりと同じぐらいメジャーだった。
4月半ばから5月5日までやっていた(鯉のぼりのように)。
つまり、浜松のオリジナルじゃなかった。
という「初凧」の話。
凧合戦が大流行した時期があった。
静岡でも浜松でも流行していた。
こちらも、浜松のオリジナルじゃなかった。
という「凧合戦」の話。
この2つが、どうやって融合したのか?
どうやって浜松オリジナルになったのか?
何が「浜松オリジナル」なのか?
たいへん読みにくい(でも面白い)、近代初頭の新聞記事なんぞを読んでしまいました。
1882年(明治15年)4月25日付の新聞記事がコチラ。

静岡県立図書館所蔵の新聞です。
(善)
今回のテーマは昨年に引き続き「凧合戦」。
今回は、「歴史」に焦点をあてて展開を致しました。
サブタイトルも「~凧揚祭前史~」。
昔は5日間だった。 →今は3日間。
昔は練兵場だった →今は中田島。
戦後の経緯の中で、「昔は~だった」という形が、現在のものへと変化していくわけです。
その「昔の姿」は、どうやって出来上がったのか。
今回は、やや踏み込んだ内容を展開。
初凧は江戸時代からあった。
初凧は農村でもあった。
今の鯉のぼりと同じぐらいメジャーだった。
4月半ばから5月5日までやっていた(鯉のぼりのように)。
つまり、浜松のオリジナルじゃなかった。
という「初凧」の話。
凧合戦が大流行した時期があった。
静岡でも浜松でも流行していた。
こちらも、浜松のオリジナルじゃなかった。
という「凧合戦」の話。
この2つが、どうやって融合したのか?
どうやって浜松オリジナルになったのか?
何が「浜松オリジナル」なのか?
たいへん読みにくい(でも面白い)、近代初頭の新聞記事なんぞを読んでしまいました。
1882年(明治15年)4月25日付の新聞記事がコチラ。

静岡県立図書館所蔵の新聞です。
(善)