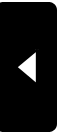2019年04月06日10:46
93日ぶりの・・・≫
カテゴリー │歴史
「93日ぶりのログイン ありがとうございます」
などと、はまぞうさんに褒められ(?)ました。
正月以来の投稿です。
さて、新元号が史上初の事前公表。
元号制度そのものの是非はともかく。
制定・発表などなど、当事者・関係の方々にあっては、たいへんなご苦労であったと、想像されます。
日本において。
「一世一元の制」(ひとりの天皇にひとつの元号)を定めたのは、明治政府でした。
代替わりごとに元号をつくる、という事自体は、長い歴史から見たらけっこう最近の話。
明治天皇の即位も「慶応3年」で、明治改元は翌「慶応4年」のことでしたから。
久しぶりの投稿。
受け継がれてきた文化としての天皇と元号(代替り・改元)を機に。
浜松において受け継がれてきた事柄について、ちょっと考えてしまいました。
さて。
浜松においては。
1880年代以降、凧合戦を繰り広げていた現在の中心部各町内において。
資産家に、その跡取りである長男が生まれ、5月に初節句を迎えると。
「おめでとうございます!!」
となり、初凧をねだり、お振舞に預かる、という、なんとも楽しい行事が発生したのですね。
初節供=初凧=お振舞というのは、各地にあったようです。
これが、「町内対抗の凧合戦」と結びついたところに浜松の特徴がある。
資産家の長男、というところがミソです。
「継承するのは長男」というのは、当時の考え方。
継承するだけの、資産や商売がある方々は、そうでない大勢の方々へ、こういう機会にお振舞をなさった、という事ですね。
お祝いに行く側は。
当該の家が、資産家であればあるほど、ついつい力が入ってしまうものです。
「おめでとうございますっ!!!」となります。
その向こうに、 おねだりとお振舞が待っているわけです。
皇位は、男系男子が継承する。
とされている旧皇室典範。
これも伊藤博文の提案で書かれたとか。
皇位継承者を含め、皇族方の減少により。
女性天皇を認めるか、それは男系女子までなのか、女系男子を認めるのか。
という議論が、ずーっとなされています。
歴史的な観点を軸に、様々な角度から、しっかり議論して頂きたいところですね。
初凧は長男誕生時。
5月の節句=端午の節句。
誕生後、初めて迎えるから初節句。
その時に揚げるから初凧。
これもまた、是非はともかく、近代に確立され戦後まで受けつがれた形でした。
我々前後の世代(私は1974年=昭和49年生まれ)は。
オレ次男だから初凧なかったよ。
というのは当たり前でしたね。
いいか悪いかは別です。
でも、「そういうもの」でした。
これがなし崩しになってしまったことは残念です。
生まれてくる子供には何の格差もないのですが。
生まれる度に初凧を出すというと、なんだか「誕生パーティ」みたいで迫力に欠けるなァという気がします。
「長男が生まれた!」「一世一代のお祝いだぞ!」
という迫力もまた、受けつがれた喜びでした。
こういう凧揚げまつりのあり方についての議論は、もっと幅広くされるべき。
と思います。
この祭をよい形で後世に残すことに必ず繫がるものと。
「93日ぶりのログイン」のタイミングは、すでに新元号「令和」発表後。
日本文化としての天皇や元号に思いを巡らせつつ。
浜松の文化としての凧揚げまつり・初凧について、久しぶりに考えてみた次第です。
(善)

などと、はまぞうさんに褒められ(?)ました。
正月以来の投稿です。
さて、新元号が史上初の事前公表。
元号制度そのものの是非はともかく。
制定・発表などなど、当事者・関係の方々にあっては、たいへんなご苦労であったと、想像されます。
日本において。
「一世一元の制」(ひとりの天皇にひとつの元号)を定めたのは、明治政府でした。
代替わりごとに元号をつくる、という事自体は、長い歴史から見たらけっこう最近の話。
明治天皇の即位も「慶応3年」で、明治改元は翌「慶応4年」のことでしたから。
久しぶりの投稿。
受け継がれてきた文化としての天皇と元号(代替り・改元)を機に。
浜松において受け継がれてきた事柄について、ちょっと考えてしまいました。
さて。
浜松においては。
1880年代以降、凧合戦を繰り広げていた現在の中心部各町内において。
資産家に、その跡取りである長男が生まれ、5月に初節句を迎えると。
「おめでとうございます!!」
となり、初凧をねだり、お振舞に預かる、という、なんとも楽しい行事が発生したのですね。
初節供=初凧=お振舞というのは、各地にあったようです。
これが、「町内対抗の凧合戦」と結びついたところに浜松の特徴がある。
資産家の長男、というところがミソです。
「継承するのは長男」というのは、当時の考え方。
継承するだけの、資産や商売がある方々は、そうでない大勢の方々へ、こういう機会にお振舞をなさった、という事ですね。
お祝いに行く側は。
当該の家が、資産家であればあるほど、ついつい力が入ってしまうものです。
「おめでとうございますっ!!!」となります。
その向こうに、 おねだりとお振舞が待っているわけです。
皇位は、男系男子が継承する。
とされている旧皇室典範。
これも伊藤博文の提案で書かれたとか。
皇位継承者を含め、皇族方の減少により。
女性天皇を認めるか、それは男系女子までなのか、女系男子を認めるのか。
という議論が、ずーっとなされています。
歴史的な観点を軸に、様々な角度から、しっかり議論して頂きたいところですね。
初凧は長男誕生時。
5月の節句=端午の節句。
誕生後、初めて迎えるから初節句。
その時に揚げるから初凧。
これもまた、是非はともかく、近代に確立され戦後まで受けつがれた形でした。
我々前後の世代(私は1974年=昭和49年生まれ)は。
オレ次男だから初凧なかったよ。
というのは当たり前でしたね。
いいか悪いかは別です。
でも、「そういうもの」でした。
これがなし崩しになってしまったことは残念です。
生まれてくる子供には何の格差もないのですが。
生まれる度に初凧を出すというと、なんだか「誕生パーティ」みたいで迫力に欠けるなァという気がします。
「長男が生まれた!」「一世一代のお祝いだぞ!」
という迫力もまた、受けつがれた喜びでした。
こういう凧揚げまつりのあり方についての議論は、もっと幅広くされるべき。
と思います。
この祭をよい形で後世に残すことに必ず繫がるものと。
「93日ぶりのログイン」のタイミングは、すでに新元号「令和」発表後。
日本文化としての天皇や元号に思いを巡らせつつ。
浜松の文化としての凧揚げまつり・初凧について、久しぶりに考えてみた次第です。
(善)